設備業界に入ると「2級管工事施工管理技士の資格を取るように!」と会社から指示されます。
そんな独学勉強法に悩んでいる受験生に、Shino40が実践してきた独学法を伝授!
- 効率的な“学科試験”独学勉強法
- 独学で合格できる“実地試験”の勉強方法
- 施工経験記述の書き方
- おすすめテキスト
- 2級管工事施工管理技士の試験概要
現在、2級管工事の模擬試験を開催中!参加希望の方は、公式LINE@に登録し『模擬試験したい』とメッセージを下さい。
もくじ
2級管工事施工管理技士の効果的な勉強方法

2級管工事施工管理技士の効率的な勉強方法は
- 過去問で勉強
- 合格基準の施工経験記述を作成
- 施工経験記述を暗記
すれば合格することができます。
2級管工事施工管理技士 学科試験の勉強方法・対策

2級管工事施工管理技士の学科試験対策で行う具体的な勉強方法は、過去問の“問題文”と“選択肢”と“解説”を流し読みして暗記する勉強方法が効果的です!
学科試験は、過去問からの出題が多いので過去問さえ暗記すれば合格できます。
また、出題方式が「四択問題」なので暗記に関しても、要点を覚えるだけで細部まで暗記する必要がありません。
過去問を読んで!読んで!読んで!過去問に目を通す量が合格の鍵となります。
解説に書かれていることを「そういうものなんだ」と受け入れることが重要です。
勉強のポイント
2級管工事施工管理技士の学科試験勉強のポイントは、2つあります。
- 過去問をなるべく多く流し読みすること(勉強量の確保)
- 絶え間ない知識のインプット(暗記の効率アップ)
となります。
時間を確保しての勉強は、当たり前として!ちょっとしたスキマ時間も勉強できるような工夫をしましょう。
それには「スマホ」を有効活用するのが一番です!
スマホに過去問データを入れておき流し読みしたり!当ブログの過去問解説記事をスマホで閲覧したり!2級管工事施工管理技士のスマホアプリを入れたり!するだけでスキマ時間にスマホを見て勉強することができます。
スキマ時間も、自分の中で「この時」と決めてしまえばルーチンとして、かなりの勉強時間を確保できると思います。
- 電車通勤時
- 車に乗った時
- タバコを吸いに行った時
- トイレに行った時
- タイマーをかけ1時間に一回
などなど…スキマ時間も日に何度も行えばかなりの時間を勉強に費やせます。
学科試験の出題傾向
2級管工事施工管理技士の学科試験は、全部で52問あり選択解答するのは40問となります。
そして合格するには24問の正解が必要となります。
2級管工事施工管理技士の学科試験は、下記の通り項目で出題されます。
| 出 題 | 出 題 項 目 | 出 題 選 択 |
| No,1~6問 | 一般基礎、電気・建築 | 6問中6問解答(必須) |
| No,7~23問 | 空調、給排水衛生 | 17問中9問解答(選択) |
| No,24~28問 | 機器材料、設計図書 | 5問中5問解答(必須) |
| No,29~42問 | 施工管理 | 14問中12問解答(選択) |
| No,43~52問 | 関連法規 | 10問中8問解答(選択) |
出題項目をくまなく勉強する必要がありますが、特に解答する数が多い「空調、給排水衛生」「施工管理」「関連法規」については重点的に勉強することが求められます。
出題項目別にどのような問題が出題されるのか説明します。
一般基礎、電気・建築
一般基礎に関しては、「空気環境」「熱」「流体」「水」などに関する出題がされます。
高校の理科などで習う用語なども問わることもありますので勉強してきた可能性はありますが得点するには、過去問から要点を覚える必要があります。
電気・建築に関しては、電気材料やコンクリートについて出題されます。建設業に携わる人間として他工種(電気工事・建築・土木)の知識を問われます。
6問中6問解答する必須問題となります。過去問からの出題割合も高いので3問は正解させましょう。
下記の様な問題が出題されます。
令和元年度【No,2】水の性状に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
- pH は、水素イオン濃度の大小を示す指標である。
- BOD は、水中に含まれる有機物質の量を示す指標である。
- DO は、水中に含まれる大腸菌群数を示す指標である。
- マグネシウムイオンの多い水は、硬度が高い。
空調、給排水衛生
空調、給排水衛生に関しては、冷暖房・排煙などの空調知識、上下水道・給水設備などの衛生知識をを問う問題が出題されます。
これ以降の問題に関しては、空調関係・給排水衛生関係の施工管理している方にとっては、仕事の知識が役に立ちます。
17問中9問解答する選択問題です。17問の中から自信のある解答を9問選択できますので、8問は正解させましょう。
下記の様な問題が出題されます。
令和元年度【No,17】給水設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
- 給水管に設置するエアチャンバーは、ウォーターハンマー防止のために設ける。
- 飲料用給水タンクには、内径60cm以上のマンホールを設ける。
- 給水管への逆サイホン作用による汚染の防止は、排水口空間の確保が基本となる。
- 大気圧式バキュームブレーカーは、大便器洗浄弁などと組み合わせて使用される。
機器材料、設計図書
機器材料、設計図書に関して、配管材料や設備機器の知識を問う問題が出題されます。
5問中5問解答する必須問題となります。過去問からも出題されますが割合は低くなっておりますが2問正解させましょう。
下記の様な問題が出題されます。
令和元年度【No,25】飲料用給水タンクの構造に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
- 屋外に設置する FRP 製タンクは、藻類の増殖防止に有効な遮光性を有するものとする。
- 2槽式タンクの中仕切り板は、一方のタンクを空にした場合であっても、地震等により損傷しない構造のものとする。
- タンク底部は、水の滞留防止のため、吸込みピットを設けてはならない。
- 通気口は、衛生上有害なものが入らない構造とし、防虫網を設ける。
施工管理
施工管理に関して、施工管理手法などの知識を問う問題が出題されます。
14問中12問解答する選択問題です。施工管理の実務経験がそのまま解答に直結問題です。また過去問の要点を押さえれば解答する事が可能な問題となっておりますので、9問は正解させましょう。
そして下記の様な問題が出題されます。
令和元年度【No,32】抜取検査を行う場合の必要条件として、適当でないものはどれか。
- 合格したロットの中に、不良品の混入が許されないこと。
- ロットの中からサンプルの抜取りがランダムにできること。
- 品質基準が明確であり、再現性が確保されること。
- 検査対象がロットとして処理できること。
関連法令
関係法令に関して、「労働安全衛生法」「労働基準法」「建築基準法」「建設業法」の知識を問う問題が出題されます。
10問中8問解答する選択問題です。過去問からの出題割合も高いので6問は正解させましょう。
下記の様な問題が出題されます。
令和元年度【No,44】労働条件における休憩に関する記述のうち、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。ただし、労働組合等との協定による別の定めがある場合を除く。
- 使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない。
- 使用者は、労働時間が 時間を超える場合においては少なくとも30分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
- 使用者は、労働時間が8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
- 使用者は、休憩時間を一斉に与えなければならない。
学科試験の勉強時間
2級管工事施工管理技士 学科試験の勉強時間について
人ぞれぞれ基礎知識の量!仕事内容!経験年数!などが違いますので一概に何時間とは言えませんが、無知識だとして10年分の過去問(52問)を3往復すれば問題の要点を覚えることができます。
勉強する総問題するは、52問×10年分×3往復=1,560問となります。あとは1問あたりにかかる勉強時間を出せば大体の勉強時間を算出することが出来ます。
それでは、時計を準備して…1問あたりにかかる時間を計測してみましょう。
H21年度問題【No,17】給水設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
- 飲料水系統と井水系統の配管を接続すると、止水弁と逆止め弁を設けてもクロスコネクションとなる。
- 給水が上水系統の場合、洗浄弁を用いた大便器には、バキュームブレーカを設ける。
- ウォータハンマを防止するためには、管内流速が小さくなるように設計する。
- ポンプ直送方式の給水ポンプは、高置水槽方式の揚水ポンプに比べて、一般に、ポンプの揚水量が小さくなる。
解説:(4)、解説:ポンプ直送方式の給水ポンプは、高置水槽方式の揚水ポンプに比べて、一般に、ポンプの揚水量が大きいなる。
さて何秒かかったでしょうか?
私は、45秒かかりました。1問当たり45秒かかるとなると
45秒 × 1,560問 = 70,200秒 = 1,170分 = 19.5時間 が勉強時間の目安となります。
学科試験のおススメの参考書
2級管工事施工管理技士 学科試験のおススメ問題集は、
過去問の定番問題集!地域開発研究所の「2級管工事施工管理技術検定試験問題解説集録版」です。
2級管工事施工管理技士 実地試験の勉強方法・対策


2級管工事施工管理技士の実地試験対策で行う具体的な勉強方法は、
過去問の問題を理解し“解答”を書いて暗記する勉強方法が効果的です!
実地試験も、過去問からの出題が多くある程度出題予想ができます。学科試験と違い実地試験は「記述問題」なので暗記に関して、細部までしっかりと暗記する必要があります。
私は、過去問を取り纏めた「暗記ノート」を作成しひたすら書いて覚えていました。
4年前の勉強時に使用した「暗記ノート」ですが欲しい方は、下記のLINE@に登録頂き「2級管工事の暗記ノートが欲しい」とメッセージを頂ければプレゼント致します。
実地試験の出題傾向
2級管工事施工管理技士の実地試験は、6問あり選択解答するのは4問となります。
2級管工事施工管理技士の実地試験は、下記の通り項目で出題されます。
| 出題 | 出題項目 | 出題選択 |
| 問題1 | 施工要領図(正誤) | 必須 |
| 問題2 | 空調設備の施工 (留意点) | 選択 |
| 問題3 | 給排水設備の施工(留意点) | |
| 問題4 | バーチャート作成 | 選択 |
| 問題5 | 法令(穴埋め) | |
| 問題6 | 施工経験記述 | 必須 |
出題項目について、個別に説明していきます。
施工要領図(正誤)《必須問題》
解答必須の問題となり、「施工要領図の適切でない部分の理由又は改善策」「機材の使用場所・使用目的」が出題されます。
出題される問題は、過去問からの出題が多くなっているのでしっかりと過去問を勉強すれば高得点が狙える問題です。
また勉強の方も、“図”が問題にあるので印象が強くなるので暗記が比較的楽に行うことが出来ます。


空調設備の施工 (留意点)《選択問題》
「空調設備工事」の施工上の留意事項を4点記載する出題となっております。
空調設備工事の施工管理に携わっている方には、実務経験の知識がそのまま役に立ちますので勉強しなくてもいいかもしれません。
しかし空調設備工事以外の施工管理者の方は、過去問で多く留意点を考えることで試験日に出題された問題に使えそうな“留意点”が必ずあります。


給排水設備の施工(留意点)《選択問題》
「給排水設備工事」の施工上の留意事項を4点記載する出題となっております。
空調設備工事同様で、給排水設備工事の施工管理に携わっている方には、実務経験の知識がそのまま役に立ちますので勉強しなくてもいいかもしれません。
また給排水設備工事以外の施工管理者の方は、過去問で多く留意点を考えることで試験日に出題された問題に使えそうな“留意点”を見出して下さい。


バーチャート作成《選択問題》
出題文にもとづいてバーチャート工程表を作成する問題です。
バーチャート作成方法さえ覚えてしまえば、満点が狙える問題です。
しかしバーチャート作成方法を覚え・作成に慣れるまで勉強時間を、結構費やすこととなります。
勉強が好きで、時間に余裕があるようでしたらバーチャート工程表の作成方法を覚え満点を獲得しましょう。
法令(穴埋め)《選択問題》
「労働安全衛生法」の穴埋め問題となります。
穴埋めと言っても、選択肢が用意されているので法令を1から覚える必要もありません。
また出題される法令文も、毎年同じですので13の条例文・出題ルールを覚えてしまえば高得点が狙える問題となっております。
バーチャート作成より法令の方が勉強時間に対するコストパフォーマンスは、高いのでおススメです。


施工経験記述《必須問題》
「品質管理」「安全管理」「工程管理」の3つのテーマに合った施工経験記述を作成し暗記することで対応は、可能となります。


実地試験の配点
2級管工事施工管理技士の実地試験について、どの様に配点がされているか公表されていませんが一般的に言われている配点は、下記の通りです。
- 問題No,1 小問5問 各4点 計20点
- 問題No,2 小問4問 各5点 計20点
- 問題No,3 小問4問 各5点 計20点
- 問題No,4 小問5問 各4点 計20点
- 問題No,5 小問5問 各4点 計20点
- 問題No,6 経験記述 40点
経験記述については、40点と大きく配点のウェートをしめていますのでしっかりと施工経験記述を準備し覚えることが必要となります。
またその他の問題も、各問4,5点と大きな配点となっているので1問差で不合格になる可能性がありますので、経験記述に勉強を集中するのではなくその他の問題もしっかりと対策をとることが重要となります。
実地試験の勉強時間
2級管工事施工管理技士 実地試験の勉強時間について
私の場合、まず問題No,6の施工経験記述を作成するのに2週間(=10時間)かかりました。
また試験勉強としては、試験1ヶ月前から勉強を始め、1日1時間(土日祝抜き)の勉強で合格することが出来ました。
施工経験記述を作成し試験勉強に費やした時間は、35時間となりました。
実地試験のおススメの参考書
2級管工事施工管理技士 実地試験のおススメ問題集は、
学科試験と同じで、地域開発研究所の「2級管工事施工管理技術検定試験問題解説集録版」となります。
実地試験の過去問解説がしっかりとされています。そして施工経験記述の記載方法の要点もしっかりと押さえられております。
また実地試験の主問題と言える施工経験記述について
市ヶ谷出版社の「2級管工事施工管理技士 実地試験 実戦セミナー」は、上司・先輩からのアドバイスが貰えない方には、施工経験記述の実例が多数掲載されているのでとても参考になります。
施工経験記述 作文作成代行サービス
2級管工事施工管理技士の実地試験は、「問題No,6の施工経験記述」が合格のカギとなります。
作成については、参考書の記述のポイントをおさえながら、上司・先輩のアドバイス、参考書から例題を参考にして作成すると良いでしょう。
しかしどうしても施工経験記述が書けない方は、「作文作成代行サービス」を使うのも一つの手です。
私が1級管工事施工管理士で、独学サポート事務局の作文作成代行サービスを使用した時の体験談・「代行作成された施工経験記述文」を下記の記事で記載しているので興味のある方は、参考にして使用するか判断されるのも良いでしょう。


2級管工事施工管理技士の概要説明


2級管工事施工管理技士試験は、一般財団法人全国建設研修センターにより開催されます。
試験の申込受付期間は、「前期」と「後期」に分かれており
- 「学科試験(前期試験)」:3月初旬から受験申込開始
- 「学科・実地試験、学科試験(後期試験)」:7月中旬から受験申込開始
となっております。
また提出書類は
- 受験申込用紙(2枚)
- 卒業証明書
- 住民票
となっており、受験申込用紙には実務経歴を記入し、卒業した学校・役所に必要書類を取りに行ったりと即時提出しようと思ってもなかなか出来ないので、受験される方は事前に準備を進めて下さい。
試験日と合格発表については、
- 「学科試験(前期試験)」:試験日 6月第1週 / 合格発表 7月初旬
- 「学科試験(後期試験)」:試験日 11月第3週 / 合格発表 翌年1月中旬
- 「学科・実地試験」:試験日 11月第3週 / 合格発表 翌年2月下旬
合格を目指すのであれば、「前期⇒学科試験」と「後期⇒実地試験」と1つの試験に勉強が集中できるようにスケジューリングすることが重要です!
ちなみに合格発表は、合格発表日10時頃に一般財団法人全国建設研修センターのホームページの「お知らせ」で見ることが可能です。
また合格通知は、合格発表日に発送すると思われますので1,2日すると到着します。
※私の場合は、合格発表時の次の日に到着しました。
2級管工事施工管理技士の受験資格・受験条件
学科試験の受験要件は、平成28年度から「受験年度中(4/1~翌3/31)に年齢が17歳以上」となっており、平成27年度以前と比べるとかなり緩和されております。
実地試験の受験要件については、「学科試験に合格していること」「最終学歴による実務経験年数を有していること」があげられます。
下記の表は、最終学歴による実務経験年数の一覧表となります。
| 最終学歴 | 管工事施工管理に関する必要な実務経験年数 | |
| 指定学科 | 指定学科以外 | |
| 大学卒業 | 卒業後 1年以上 | 卒業後 1年6ヶ月以上 |
| 短期大学卒業 | 卒業後 2年以上 | 卒業後 3年以上 |
| 高等学校卒業 | 卒業後 3年以上 | 卒業後 4年6ヶ月以上 |
| 最終学歴問わず | 8年以上の実務経験年数 | |
ちなみに実務経験と認められる工事は
- 受注者として施工を指揮・監督した経験
- 発注者側における現場監督技術者等としての経験
- 設計者等による工事監理の経験
となっております。
詳しくは、下記の記事を参照下さい。


2級管工事施工管理技士の合格率と難易度、合格基準
2級管工事施工管理技士の学科試験合格率は、平均56.1%となっております。
国家資格として2人に1人が合格できるので、それほど難しい資格ではありません。試験内容が四択問題なので、無勉強でも基礎知識があり運が良ければ合格が出来てしまう試験です。
下記の表は、平成19年度から零和元年度の学科試験の合格率と受験者数の推移となっております。


ここ5年に関していえば合格率が高水位で推移しており、平成28年度で66.2%、平成30年度前期で61.7%と今までにない合格率となっております。
これは技術者不足を補おうと試験が簡単な傾向に向いているのではないかと推測出来ます。裏付けるように受験者からは「過去問から沢山出題された!」「それほど難しくはなかった」などの声が聞かれました。
続いて2級管工事施工管理技士の実地試験合格率は、平均39.2%となっております。
実地試験に関しては、学科試験と違い論述問題なのでしっかりと受験準備して勉強しないと合格することはできません。しかし施工経験記述を用意し、過去問を勉強すれば合格することが出来るので、難しい部類の試験ではありません。
下記の表は、平成19年度から零和元年度の実地試験の合格率と受験者数の推移となっております。


学科試験と同じで、ここ5年合格率が高水位で推移しており平成27年度が45.9%、平成28年度が44.5%と合格率の推移が1段階上がっています。
まとめ
2級管工事施工管理技士を合格するための効果的な勉強方法は、「過去問」を使用することです。私が今まで取得した施工管理技士は、全て過去問をベースにした勉強方法で独学で合格できております。
実地試験の「施工経験記述」について、ポイントをおさえて専門用語をいれながら記述すると高得点が狙えます。また出来ることなら大規模な物件について記載すると、課題など沢山考えられるのでおススメです。
最後に2級管工事施工管理技士について悩んでいることがありましたら、気軽に「LINE@」にメッセージを下さいね。
また管工事施工管理技士の情報を、時々配信しております。もし需要があれば無料の勉強会なども開催したいと思っております。
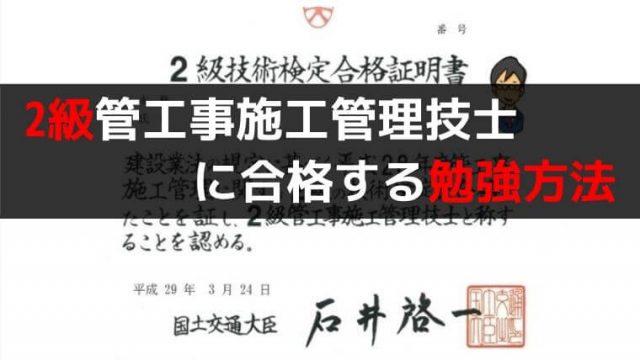

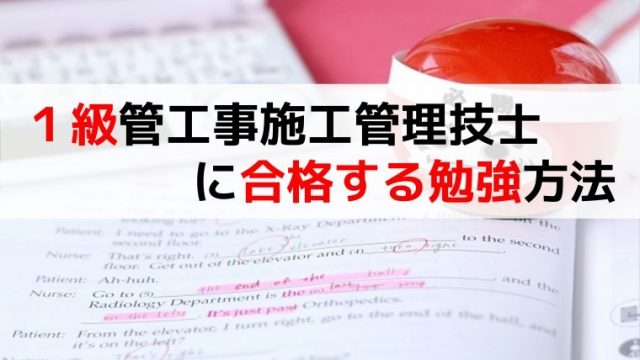

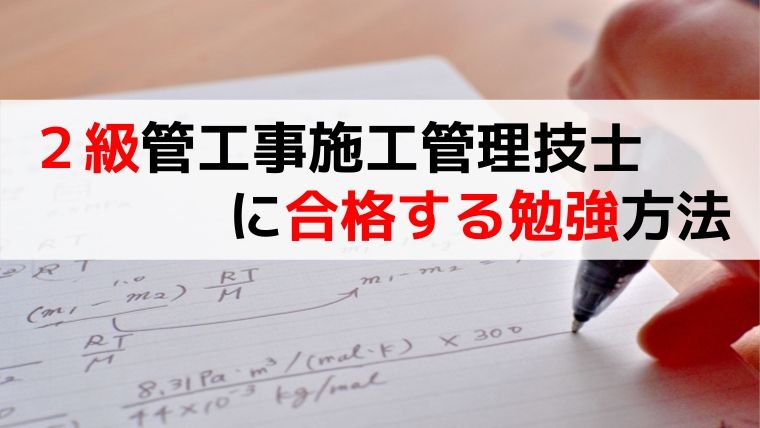

M.gif)

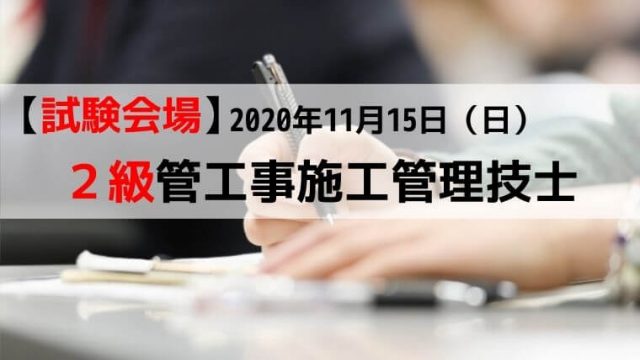

M-150x150.gif)